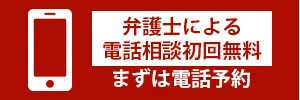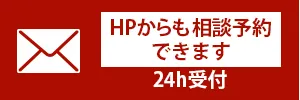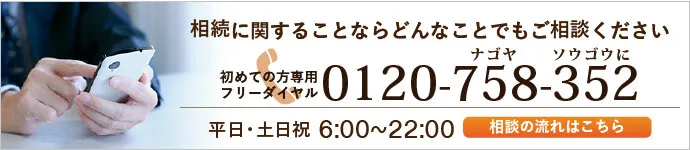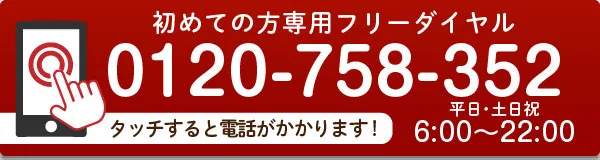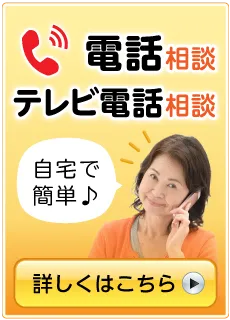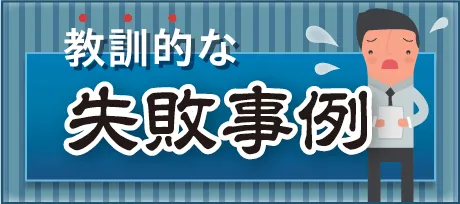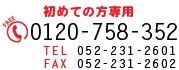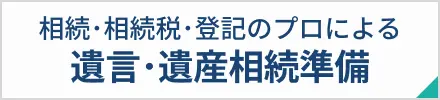相続の問題で、相続分や遺言で指定された持ち分を変更する制度として、「寄与分」と「遺留分」という制度があります。

まず「寄与分」という制度ですが、これは被相続人の財産の増加や維持に貢献したり、被相続人の財産の減少を食い止めた相続人がいた場合に、そのような被相続人に対する特別な貢献のある相続人と、そうでない相続人の間の不公平を調整するための制度です。
民法では、904条の2として、以下のような内容が定められています。
「1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算出した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」
つまり、特別の寄与(貢献)があった相続人には、まず遺産全体の中から寄与分に相当する部分を取り除き、残ったものを通常は法定相続分で分け、寄与分がある相続人には寄与分相当額を相続分に上乗せする、ということを定めています。
遺産分割で具体的にどのような遺産を取得するかは協議等によりますが、寄与分があるとその分、相続分が増えるという関係にあります。
寄与分に関して話し合いで解決することができない場合には、家庭裁判所が寄与分を定めることができますが、その基準は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮することになっています(民法904条の2 2項)。
寄与分が認められる場合として代表的な例は、例えば家族の事業に給料をもらわず無償で協力してきた場合や、被相続人に扶養料を支払って生活を支えてきた場合、被相続人が介護施設に入所するような重い介護状態にあったのに自分や家族で介護して介護費用がかからなかった場合が多いでしょう。
なお、寄与分は、相続開始の時にあった財産額から遺贈額を超えた残りの額を超えることができませんし(民法904条の2 3項)、裁判所に寄与分を求められるのは、民法第907条2項に規定する請求があった場合(遺産分割に関して共同相続人間に協議が調わず、家庭裁判所に遺産分割の請求をした場合)又は民法第910条に規定する場合(相続の開始後に認知によって相続人となった者がいる場合で、遺産分割をしようとしたが既に他の共同相続人が遺産分割等の処分をしていた場合)に限られています(民法904条の2 4項)。
つまり寄与分は、寄与分に争いがある場合に寄与分単独で決めてもらうように裁判所に請求することはできず、基本的には他の遺産分割の請求とセットでしなければ、裁判所に決めてもらうことができないということです。
次に遺留分ですが、その計算方法は民法1046条2項に定められています。
遺留分の計算方法としては、「民法1042条の規定による遺留分」-「遺留分権利者が受けた遺贈や特別受益(生前贈与)」-「遺留分権利者が取得すべき遺産額」+「被相続人が相続開始の時において有した債務のうち遺留分権利者が承継する債務」で計算されることになっています。
ここで、寄与分との関係を見ますと、寄与分があれば相続分が増えることになりますが、争いがあると寄与分は遺産分割とセットでしか解決することができません。
そうしますと、遺留分では、通常は生前贈与や遺言書がある場合など遺産分割で解決できない場合の制度ですので、仮に生前贈与や遺言書によって遺産が全て(又はほぼ全て)どのように分けるか決められていれば、寄与分を定めることができず、結果として寄与分が認められない可能性もあります。
他方で、寄与分の上限は遺産額から遺贈額を引いた金額ですので、理屈上は寄与分の金額が遺産額と同等か上回っていれば、全て寄与分を持つ相続人が遺産を取得し、他の相続人は遺産を取得しないということもあり得ることにはなります。
このような場合に遺留分が認められるかといえば、寄与分で定めたものを遺留分で覆すことができるとすると安定性を害しますし、また寄与分は遺留分侵害額請求の対象とは明示されていませんので、遺留分により寄与分を覆すというのは難しいでしょう。
ただし、仮にそうだとしても、現在の裁判所の運用実務では、寄与分が認められる場合でも裁量的に減額をされることがあり、遺留分を侵害するような多額の寄与分を裁判所が認めるということは、難しいのではないかと思われます。
事務所外観

名古屋丸の内事務所

金山駅前事務所

一宮駅前事務所

岡崎事務所
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会