Aさんは夫が亡くなり、残された財産は自宅不動産くらいでした。
Aさんは生活費に困っていたため、自宅不動産を売却しようと相続人を確認すると、子供がいなかったため夫の兄弟が相続人になりますが、夫の兄弟が多数いることが分かりました。Aさんは、自分では対応できないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、他の相続人に対してできる限り相続分譲渡をしてほしいという交渉をした上で、応じなかった相続人や連絡の取れない相続人がいたことから、裁判所に遺産分割審判を申し立て、速やかに進める方法をとりました。
裁判所に法的手続を申し立てた結果、連絡の取れなかった相続人からも連絡があり、最終的には裁判所の決定という形で、Aさんが遺産を取得し、不動産を売却した上で、代金から諸費用等を控除した金額を他の相続人に分配するという内容で解決を図ることができました。
約1年6か月
配偶者は相続の順位としては、第1位の相続人と同列という扱いになっています。夫婦間に子供がいないと、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になることになります。そうしますと解決にかなりの労力を要する可能性がありますので、このような場合には事前に遺言書を作っておいた方がいいでしょう。
Aさんは、遺言で実家を含む財産一切を相続しました。しかし、兄弟から遺留分減殺請求がなされ、不動産の一部(遺留分割合の持分)を渡すように求められ、話し合いが決裂しました。
すると、兄弟はAさんに対して訴訟を起こし、同時に過去の被相続人の預金口座からの引き出しが不当利得だとして、その不当利得返還請求訴訟も起こしてきました。
自分では訴訟に対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話を聞き、実家の遺留分については価額弁償による金銭解決を図ることにしつつ、預金口座から引き出された金銭は、被相続人の生活費に使われたり、他の口座に移動しているだけであったり、介護に関する費用に相当する部分があったりしましたので、そういった点を主張した結果、裁判所から和解の提案がなされ、当初の請求から大幅に減額した内容で和解が成立しました。
約1年
生前に被相続人の預金が引き出された等の理由から訴訟を提起された場合、不当利得返還請求として請求される場合が多いと思われます。
このような場合、誰が引き出したか、引き出した金銭の使途が大きな争点になります。
引き出した金銭の使途が曖昧な場合には、引き出された金額、使途、頻度、生前の被相続人の生活状況などを総合的に考慮して判断されることが多いようです。
弁護士 杉浦恵一

相続の際に、遺産の中に賃貸物件(収益物件)が含まれていることがあります。
近時では、ワンルームマンションの1部屋単位の投資もありますので、こういった賃貸物件(収益物件)が遺産に含まれることも増えてくるかもしれません。
建物など不動産を賃貸借する際には、一般的に敷金・保証金といった将来返還する必要のある金銭を受け取っている可能性があります。
最近では、敷金のない物件も増えているようですが、やはり退去時の原状回復費用の担保として、敷金・保証金といった名目で金銭を預かっている場合の方が多いでしょう。
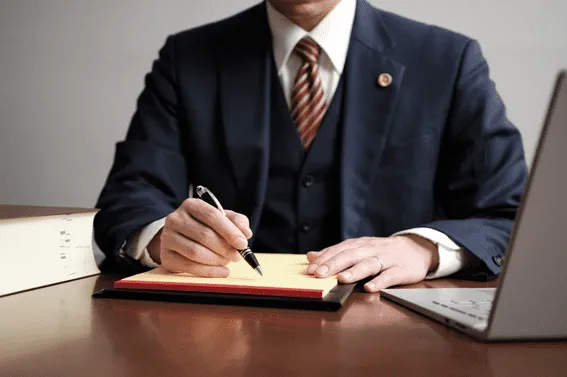
改正民法では、その605条の2の第4項で、
第一項または第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び622条の2第一項の規定による同項に規定する金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
と定められました。
つまり、敷金を差し入れた後、賃貸物件が売買などで譲り渡された場合には、
ということになります。

他方で、相続における負債の扱いは、相続人間で誰かが負債を引き受けるという合意でもない限り、法定相続分によって分割されることが一般的な考え、取り扱いです。
相続人の間で合意したり、遺言で負債を負う相続人を決めるなどして、変更することもあり得ますが、債権者は相続人に対して、法定相続分で請求できると解釈されています。
ただし、敷金も賃貸物件の賃貸借が終了し、明渡をする際に返還する義務が発生しますので、負債の一種と言えます。

では、賃貸物件を相続し、敷金返還の債務も相続した場合、これは賃貸人(=賃貸物件を相続した相続人)が全部を負担するのか、相続人が法定相続分で返還義務を負うのか、どちらでしょうか。
この点について、大阪高等裁判所の令和1年12月26日判決が参考になります。

この事件は、
大阪市内に所在する建物の賃借人であった控訴人が、賃貸人に対して敷金として3000万円を差し入れていました。
しかし、賃貸人が死亡してしまいました。
そのため、死亡した賃貸人の相続人に対して、返還を求めました。
具体的には、「法定相続分に応じて敷金の返還債務を分割して相続した」として、「敷金返還額のうち法定相続分で按分した額」を請求した。
という事件でした。
この事件で、裁判所は、
敷金は、賃貸人が『賃貸借契約』に基づいて賃借人に対して取得する債権を担保するために差し入れされるものである。
したがって、敷金に関する法律関係は賃貸借契約と密接に関連し、「賃貸借契約に随伴すべきもの」と解される
と解釈基準を示しました。

そして、賃貸人が変更した場合に、
賃借人が旧賃貸人から敷金の返還を受けた上で、新賃貸人に改めて敷金を差し入れる労力と、
旧賃貸人の無資力の危険性から賃借人を保護する必要性
を考慮すると、
賃貸人の地位が承継された場合には、敷金に関する法律関係は新賃貸人に当然に承継されるものと解される
と述べました。

裁判所は、その上で、
・敷金が担保となっている性質
・賃借人を保護する必要性
は、
で何ら変わるわけではない
としました。
この理由から、
相続で賃貸物件を承継した場合であっても、当然に相続人間で敷金返還債務が分割されるのではない。
「賃貸物件を相続した相続人」が敷金の返還債務を負う
(つまり賃貸物件を相続した相続人が、単独で敷金返還債務の全部を承継する)
と判断しました。

なお、この事件の判決では、
「相続人間で敷金返還債務について承継割合を定めた具体的な協議がされた」
とは認定されておりません。
加えて、
「敷金返還債務を法定相続分に従って分割承継するという合意が成立した」
とも認められないと言及されています。
このことから、
相続人間で敷金返還債務を、賃貸物件を相続した相続人が単独で承継するのではなく、「相続人間で分割承継する」という遺産分割協議が成立していた
といった場合には、別に理解する余地も残されているようです。

このように、相続であっても賃貸物件や敷金返還債務の場合には、負担が大きくなる相続人も出てくる可能性がありますので、注意が必要でしょう。
「敷金が高すぎて返還できない」「賃貸物件を継がないのに、敷金返還の分割を請求された」など、お悩みのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
遺言執行者には、就任した際に相続人へ通知を行う法的義務があります(通知義務)。この通知義務は、民法の改正により明文化されたものであり、相続人との間で不要なトラブルを防ぐためにも非常に重要です。

改正前民法では、遺言執行者が就任した場合、遺言の内容を相続人に対して通知しなければならない旨の規定は存在しません。
規定が存在しないため、遺言執行者は通知をしません。
そのため、後日事情を知った「相続財産を取得しない相続人」との間で問題が生じることがあり得ます。
なお、弁護士や司法書士等は遺言執行者に就任する場合に、相続人へ、
「遺言執行者に就任した旨の通知」
と共に
「遺言内容や財産目録」
を通知するのが通常です。
令和元年7月1日に民法が改正されました。
遺言執行は適正に行われなければならないという観点から、 遺言執行者はその就任後に「その旨をすべての相続人に通知すること」を義務づけるという規定が新設されました。

| 第1007条 改正民法 | |
|---|---|
| 1 | 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わねければならない。 |
| 2 | 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 |
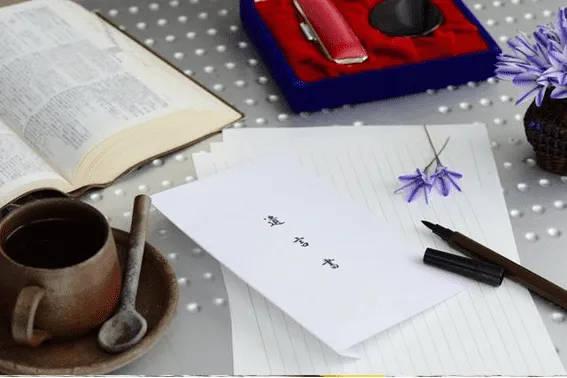
この通知義務の内容は、その「就任の事実」だけを通知するだけでは不十分で「遺言書の内容」まで相続人に知らせるべきでしょう。
具体的には遺言書のコピーを添付して相続人に通知することが考えられます。
通知はすることになりますが、遺言執行者はだれに通知すべきでしょうか?
民法の規定から見ますと相続人を対象としていて、相続人以外の遺贈等による受遺者は通知の対象としていません。
これについては、相続人は遺言による相続手続きの履行や遺留分侵害額請求をするため、遺言内容や遺言執行者の有無につき利害関係を有しているから対象とされている一方、遺贈の特定受遺者に関しては相続人に比して必要性が低いと考えられているようです。

ただし、同じ遺贈でも包括受遺者(遺産の全部または割合的な一部分を遺贈された者)は民法990条により相続人と同一の権利義務を有すると規定されていることから、遺言執行者の通知が必要であると考えられます。

遺言執行者は、就任時の通知の他にも、相続人や包括受遺者から請求されたときは、いつでも遺言の執行状況を報告する義務があります。
また、遺言の執行が終了した場合、遺言執行者は、相続人や包括受遺者に対して、遅滞なく経過及び結果を報告しなければなりません。
併せて読みたい記事>>遺言執行者の報酬は必要?
併せて読みたい記事>>亡くなった叔母の遺言書で、遺言執行者に指定されていた事例(岡崎事務所/相続の解決事例)

被相続人:Aさんの父
相続人:Aさん、Aさんの兄
依頼者:Aさん
Aさんは、父が亡くなったため、兄と遺産分割協議をする際に、遺産の整理などを兄に任せていました。しばらくして兄から、不動産などの遺産は兄が全て取得し、Aさんには預金の一部だけ取得させる内容の遺産分割協議書が一方的に送られてきたため、Aさんは自分で話をするのは困難だと思い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
預貯金の履歴を調べると、生前に父の口座から兄にある程度の金銭が振り込まれていることが分かり、この点を争うことも考えられましたが、Aさんは早期解決を希望していたため、生前の金銭については争わないという条件で、不動産を概ね半分ずつ分割し、価値の差額を代償金で支払ってもらうということで、早期に解決しました。
生前に被相続人の口座から引き出しがあったり、相続人の口座へ送金があることもあります。このような場合、損害賠償請求権や不当利得返還請求権を相続したということで、遺産分割とは別に争うこともあります。
ただ、かなり時間と労力もかかりますので、こういったことを不問にして、遺産分割を早期に解決するという方法も考えられます。
約3か月
9月14日に名古屋家庭裁判所に遺産分割調停申立事件について家事調停を申立てました。
8月4日に名古屋家庭裁判所に特別代理人選任申立事件について家事審判を申立てました。
8月18日に名古屋家庭裁判所に遺産分割調停申立事件について家事調停を申立てました。
8月18日にさいたま地方裁判所熊谷支部にて共有物分割請求控訴事件の確定判決に基づき、競売開始決定が出ました。
8月23日に東京地方裁判所立川支部にて遺留分減殺請求事件について和解が成立しました。
8月26日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。
7月1日に徳島家庭裁判所に相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。
7月5日に徳島家庭裁判所に相続放棄申述受理申立事件について相続放棄申述が受理されました。
7月20日に名古屋家庭裁判所半田支部に相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。
6月3日に山口家庭裁判所周南支部に相続放棄申述申立事件について相続放棄申述が受理されました。
6月16日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述が受理されました。
6月16日に東京家庭裁判所に相続放棄申述が受理されました。
6月16日に東京家庭裁判所に相続放棄申述が受理されました。
6月17日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割調停が成立しました。
6月22日に名古屋家庭裁判所にて遺言無効請求について和解が成立しました。
6月23日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述が受理されました。
6月23日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述が受理されました。
6月30日に名古屋高等裁判所にて更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件について判決が言い渡されました。
4月6日に名古屋家庭裁判所に請求すべき按分割合に関する処分申立事件について審判が確定しました。
4月8日に名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されました。
4月8日に名古屋家庭裁判所に後見開始の審判申立事件について審判が確定しました。
4月14日に岐阜家庭裁判所中津川出張所に相続申述が受理されました。
4月19日に山口家庭裁判所周南支部に相続放棄申述受理申立事件 について家事審判を申立てました。
4月28日に岐阜家庭裁判所多治見支部に相続放棄申述受理申立事件 について家事審判を申立てました。
3月10日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて遺産分割調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月10日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて遺産分割調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月12日に名古屋家庭裁判所にて遺留分侵害額の請求調停事件について調停が成立しました。
3月19日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。
3月19日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。
3月25日に名古屋家庭裁判所にてて審判前の保全処分(仮分割仮処分)申立事件について審判が出ました。
3月31日に名古屋高等裁判所にてて後見開始の審判に対する即時抗告事件について決定が出ました。
2月12日 名古屋家庭裁判所岡崎支部に、成年後見開始申立事件について家事審判を申立てました。
2月16日 さいたま家庭裁判所にて、遺産分割調停事件について調停が成立しました。
1月4日 名古屋家庭裁判所にて、遺産分割調停事件について調停が成立しました。
Aさんは、叔父が亡くなったため、被相続人の兄弟と遺産分割の話をしていましたが、きちんと相続人を確認していませんでした。いざ相続人を確認すると、以前に亡くなっていた叔父の兄弟に子供がおり、この子供達も相続人になることが分かりましたが、親族の付き合いがなく住所等の連絡先が分かりませんでした。自分では対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、住所を調査し、亡くなった兄弟の子にそれぞれ手紙を出して連絡したところ、いずれの兄弟も、法定相続分でなくてもいいので一部遺産はほしいということでした。
そのため、簡易に解決するため、遺産分割が終わったらAさんから代償金を払う代わりに相続分を譲渡してもらい、Aさんと叔父の兄弟で遺産分割を行って、相続手続きを完了させました。
兄弟姉妹は疎遠になることがあり、兄弟姉妹の相続では、亡くなった兄弟姉妹の子にも代襲相続権があります。そのため、知らない親族も含めて遺産分割の話をしなければならないこともありますので、注意が必要でしょう。
約6か月
Aさんは、兄弟が亡くなったため、遺産分割のため戸籍を集めたところ、かなり前に養子に出された兄弟がいることが分かったり、直近でなくなった兄弟よりも前に亡くなった兄弟が、実は養子であり、その養子の親が相続人になることが分かるなど、相続関係が非常に複雑であることが分かりました。
自分では対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、相続人の住所を確認した上、手紙を出して相続に関する意向を確認し、意向をとりまとめて話し合いで遺産分割を成立させることができました。
続人は戸籍謄本を取得して確認することになりますが、実際に確認すると養子がいたり、認知した子がいたりと、知らない親族がいることもあります。
この傾向は、過去の時期ほど多いようですので、遺産分割の際には思わぬ相続人がいないか注意が必要です。
約3か月
夫が亡くなった時、のこされた妻は、一緒に住んでいた夫名義の家にそのまま住み続けることができるでしょうか?

「配偶者居住権」とは、
① 亡くなった人(被相続人)の所有する居住建物に住んでいる配偶者が、
② 亡くなった人(被相続人)の相続開始後も、
③ 配偶者のために居住建物の所有権を取得するのではなく、
「処分権限のない使用収益権限のみを取得する」ことにより、
④ 遺産価値を収縮させた居住権を確保させ、
収縮させた遺産価値の分金銭を取得することができる制度です。
配偶者居住権の成立要件は下記の2つです。
| 1 | 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していたこと |
|---|
「配偶者」には内縁の配偶者は含まれません。
目的となる「建物」は、相続開始時、被相続人の相続財産(生前所有していた)でなければならず、被相続人が借りていた建物は含まれません。
また被相続人が建物の所有権を単独でなく共有持分を有していた場合は、被相続人の配偶者(以下、「配偶者」)との間で共有している建物以外は「建物」に含まれません。

「建物」が店舗兼住宅であった場合も店舗部分も含めて建物全部に配偶者居住権を取得できます。
「建物」の一部が相続開始前から第三者に賃貸されていた場合、配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の相続開始後の建物所有者(以下、「建物の所有者」)との関係では、第三者に賃貸されている部分も含め、建物全部について使用収益できる権利を取得します。
ただ相続開始前から賃貸している賃借人は賃貸人たる地位を承継した建物所有者に賃料を支払います。
「居住していた」とは配偶者が被相続人の建物を生活の本拠としていたこと、です。
配偶者の住民票上の住所が居住建物にあるだけでなく、実質的に判断されます。
例えば、相続発生時に施設や病院に入所・入院していて、実際に住んでいなかったという場合は原則「居住していた」となりません。
しかし、配偶者の家財道具が建物に残してあり、入院が一時的で建物に帰ることを予定していれば「居住していた」ことになりえます。
| 2 | その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈、死因贈与がされたこと。 |
|---|
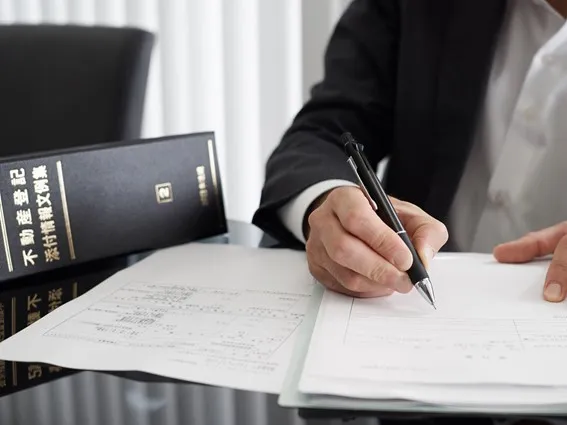
「死因贈与」は改正民法第1028条には規定はないですが、民法第554条によりその性質に反しない限り遺贈の規定が準用されることとなっています。
「遺産分割」には遺産分割の審判も含まれます。
または
は、仮に他の相続人が反対していても配偶者居住権を取得可能です。
遺言書で配偶者居住権を相続させる、という条項があっても配偶者に配偶者居住権を取得させることはできず、その条項は無効です。
但し、遺言者が無効の遺言書を作成したとは考えにくいので、配偶者居住権を遺贈をしようとした、と解釈できないかを検討することになります。
相続で、住みなれた家に住めなくなるのは困りますよね。
義理の家族との話し合いも、気を使ってしまいますよね。
一人で悩まずに、ご相談ください。私たちが味方になります。
弁護士 杉浦恵一
今年の4月21日、相続や共有の不動産、所有者不明土地の解消に向けて、色々な法案が可決されることになりました。

今後、順次施行されていきます。
困ったときに使える可能性もありますので、今後の運用や使われ方などに注意していった方がいいでしょう。

これまでの民法では、共有物について、「保存」・「管理」・「処分」といった考えがありました。
民法の改正により、この辺りの考え方がやや明確になりました。
共有者の中で、所在が不明な者がいるケースがあります。
その場合、裁判所の関与の下、公告等を行った上で、所在が判明している残りの共有者で共有物の変更ができるといった制度が創設されました。
共有関係の解消に関しては、共有物の分割方法が明文化され、はっきりとしました。
相続開始から10年間を経過したことなど所定の要件を満たした場合。
遺産として共有になっている不動産を、共有物分割訴訟によって分割することができるように法改正されました。

相続が発生しますと、不動産は相続人間で共有となります。
遺産分割が終了するまでは、共有状態が継続します。
ですから、いきなり「共有物分割の裁判」は出来ないと考えられてきました(最高裁判所昭和62年9月4日判決)。
そのため、これまでは遺産の中に不動産があった場合には、まず遺産分割協議を行っていました。

遺産分割の中で共有になった後で、共有状態を解消できない場合には、共有物分割裁判をするという流れになっており、非常に手間がかかることがありました。
今回の法改正で、相続開始から10年を経過したこと等の要件を満たす必要はありますが、かなり古い遺産が放置されている場合などには、いきなり共有物分割訴訟を起こすことができ、便利になった可能性はあります。
ただ、改正民法では、相続人が異議の申出をすると、いきなりの共有物分割はできない場合もあるようです。
必ずできるわけではない点に注意は必要です。
今回の法改正で、所有者が不明な土地についても、利用しやすい仕組みに変わりました。

所有者不明の土地でも、必要に応じて、利害関係人が請求すれば、裁判所が「所有者不明土地管理人」による管理を命じることができるようになります。
相続の分野では、
| 「相続財産管理人」の規定が見直された |
| 相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分の規定が適用されなくなったり、法定相続分や指定相続分で分割しなければならなくなった |
上記のように、遺産分割をせずに放置した場合のペナルティのようなものが設けられるようになりました。

このような点がありますので、遺産分割は特別な事情がない限り、速やかに行った方がいいと考えられます。
他方、特別受益や寄与分を主張されたくない相続人は、
敢えて長期間、遺産分割をしないという方法をとる可能性も出てきます。

一連の法改正により、所有者が不明な土地の発生を防止するため、
これまでは、相続の登記はいつまでにしなければならないという義務はなく、かなり長期間にわたって名義変更されないまま、さらに2、3回の相続が発生して更に複雑化するということもありました。
正当な理由なく登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料に処される可能性があるということで、注意が必要でしょう。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会